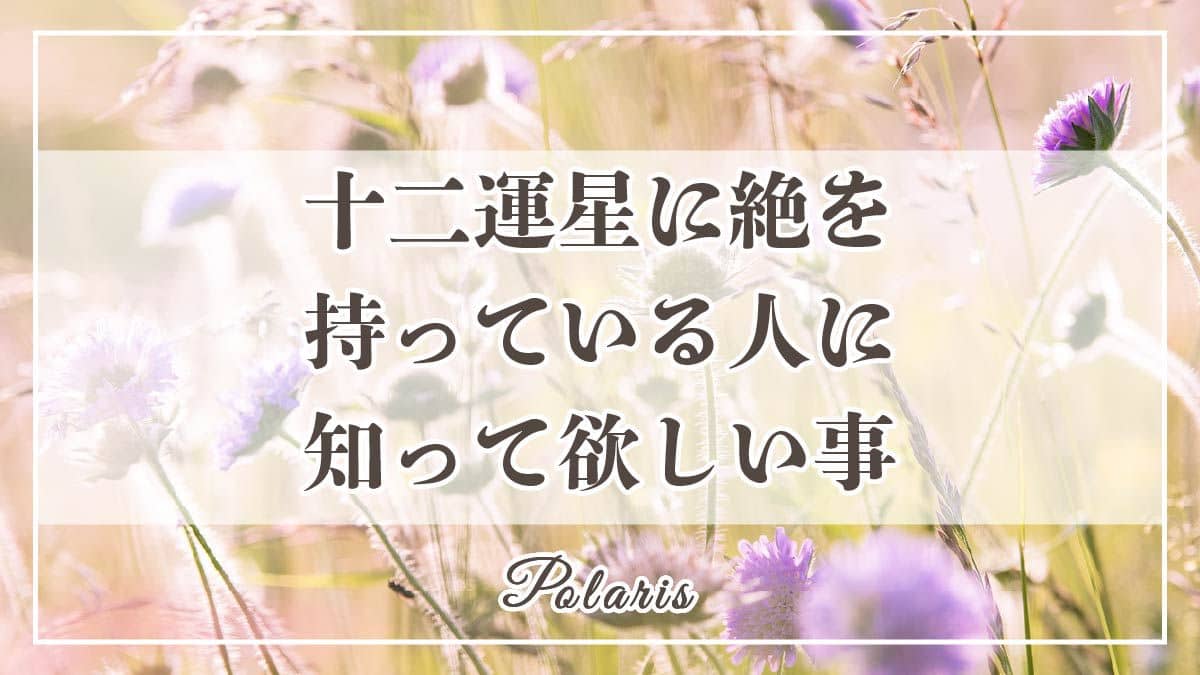十二運星に絶がある人は、精神的に繊細なタイプが多いです。
人が気にならないことが気になったり、周囲の環境に影響されやすかったりなど、「生きにくいな」と感じることがよくあるのではないでしょうか?
もちろん、他の星との兼ね合いや、どの位置に絶があるかにもよりますが。
- 絶を持っている人が生きやすくなる方法
十二運星の絶(ぜつ)とは

十二運星の絶とは、あの世の魂の星とも言われています。
絶のキーワードは、下の通りです。
- 精神的孤独
- 繊細さ
- 非日常性
- 天才性
これらのキーワードからも、ちょっと生きにくい印象が伝わってきます。
絶を持っている人の気質

絶を持っている人の気質は、感受性豊で小さなことにとても敏感です。
色々なことを人よりも強く受け止めたり、感情の波が激しくなったりなど、様々な出来事に翻弄されやすく、精神的に少し疲れやすいタイプとも言えます。
また、孤独を感じやすい寂しがり屋ではありますが、案外一人でいることが好きだったりします。
絶を持っている人が求めるもの
絶を持っている人が求めるものは、この世で色々な体験をし、どんなことでも全て味わい尽くしたいというものです。
なぜそう求めるのか?と疑問に思われるかも知れませんね。
冒頭にも触れましたが、絶という星は「あの世の魂の星」と言われています。
いったいあの世とは、どんな所なのか想像してみてください。
私はあの世に行った記憶がないので何とも言えませんが、ここで言う「あの世」とは、無の世界だと仮定してもらえたらと思います。
では、「無の世界」とはどんな所なのでしょうか?私はおそらく、下記のような所だと思います。
- 永遠で、不幸も幸せもない世界
- 辛いも楽しいもない世界
- 空腹も満腹も美味しいもない世界
- 誰かと話したり交わることのない世界
- 感覚 (触覚) も感情もない世界
もしあなたが無の世界にいたならば、この世に生まれたら「色々な体験をして、どんなことも全て味わい尽くしたい」と望むと思いませんか?
絶が命式にある人は、このような感性の持ち主なのです。
絶を持っている人の傾向

絶を持っている人の傾向は、怖いこと・不安・心配ごとなどを持ちやすいです。
これらは誰でも感じることですが、絶を持っている人は、こういったことを人よりも強く感じる傾向があります。
このため、変化を怖がり人一倍安定を求めるようにもなります。
しかし、魂的 (無意識下では) には、変化の少ない平凡な日々を望んでいないので、安定ばかりを求める選択をし続けると、逆に不安定を引き寄せることもあります。
では、どうすればいいのか?と言いますと、なんでもいいので新しいことにチャレンジしてみてください。

安定を求めて安心安全に生きることにエネルギーを注ぐより、「やりたい!」「楽しそう!」と感じることにエネルギーを向けてみましょう。
何かに挑戦すると、成功することもあれば、失敗して悲しかったり落ち込んだりもします。
そういった心の浮き沈みも、絶を持っている人は体験したいと望んでいるわけですから。
(*無意識下なので思考では浮き沈みを望んではいません。)
絶を持っている人に必要なこと

絶を持っている人に必要なことは、リラックスする習慣と安心できる環境です。
いくら魂的に「色々な体験をして、どんなことも全て味わい尽くしたい」と望んでいたとしても、浮き沈みが激しいと疲れます。
なんでもない平凡な毎日ですら、些細なことをいっぱい感じているわけですから。
また逆に、安心してリラックスしているからこそ、些細な素敵な出来事も感じることができます。
例えば、窓の外から聞こえる小鳥のさえずりに穏やかさを感じたり、風になびいている木々を見て、風と木が遊んでいるようで楽しい気分になったりなど。

緊張していたら、こういった些細なことを感じられません。絶をもっている人の感受性は、リラックスしてこそ良い方向に発揮されるので。
リラックスした心ががなければ、なにをやってもただ怖いだけになってしまいます。自分なりの安心できる環境を整えることも大切です。
以上、絶を持っている人に知って欲しい事をご紹介しました。
お読み頂き、ありがとうございました。では、次回記事にてお会いしましょう。