
十二運星って縁起が悪い漢字ばかりで、なんだか怖いですね。



確かにそうですね・・・。
十二運星の漢字は「病・墓・死」など、縁起が悪いイメージの漢字がいくつか使われています。そのため怖いと感じている人が多いのではないでしょうか?
でも、ご安心を。十二運星は、漢字から想像する悪いイメージとは関係ありません。
こういった感じが使われている理由は、人が生まれてから亡くなるまでの過程を12段階で表しているからです。決して、この先の運命を示唆しているのではありません。
故に、「死」という星があるから縁起が悪い・早死にするという意味ではく、それは「病」や「墓」などにも同じことが言えます。
無駄にネガティブにならないようにしてください。
十二運星が意味するもの
十二運星の個性や感性
では、十二運星の本当の意味を紹介していきます。
十二運星が意味するものは?


十二運星が意味するものは、人の無意識下にある「感覚や感性」を表しています。
つまり、その星を持っている人が、どのような個性や感性を持っているのか?という事が分かります。
星によってどう違うのか?については、十二運星の持っている人生のストーリー(段階)から知ることができます。
十二運星が表す人生のストーリーとは?
十二運星が表す人生のストーリーは、下の表のとおりです。人が生まれてから魂に戻るまでの流れを表現しています。
| 星の種類 | 人生の段階 |
|---|---|
| 胎 | 胎児の星 |
| 養 | 赤ちゃんの星 |
| 長生 | 幼児期の星 |
| 沐浴 | 思春期の星 |
| 冠帯 | 青年期の星 – 女王様 – |
| 建禄 | 成人期の星 – 王子様 – |
| 帝旺 | 壮年期の星 – 王様 – |
| 衰 | 老年期の星 – 長老 – |
| 病 | 病人の星 |
| 死 | 死者の星 |
| 墓 | お墓の中の星 |
| 絶 | あの世の魂の星 |
人はそれぞれ、考えること・行動・感じることが違いますが、その違いは、持っている十二運星によって変わる部分があります。
例えば「沐浴」は、思春期を象徴している星です。この星を持っている人は、思春期に持つような感性のタイプと言えます。
自分の十二運星をは、下のリンク先から調べられます。
命式をチェック
- リンク先は、風水デザインにこだわった開運パワーストーンアクセサリー専門店 Magic Wandsさんのサイトです。
下のサンプル命式の、青く囲っている場所が十二運星です。


時柱の欄を出すには、生まれ時間の入力が必要ですが注意点があります。正確な生まれ時間の出し方は、下の記事をご覧ください。
それぞれの十二運星について、詳しく見ていきます。
十二運星から分かることは?
十二運星から分かることは、その星を持っている人のおおまかな印象などです。また、その人の「悩みの傾向・個性・生かし方」なども分かります。
それぞれの十二運星の特徴を紹介していきます。
① 胎(たい)お腹の中の赤ちゃんの星
胎は、お腹の中の赤ちゃんの星です。


胎が象徴するのもは?
胎が象徴するものは、お腹の中の赤ちゃんの好奇心です。
お腹の中ですくすくと育っている赤ちゃんは、どんなことを感じているのでしょうか?
もしかしたら、「いつ生まれようか?」「生まれたら何しよう?」「あれもこれも楽しそう!」。こんなふうに、希望に胸を躍らせながら、誕生する日を楽しみにしていかも知れません。
胎を持っている人は、そんなワクワク感を大切にするタイプです。
- お腹の中の赤ちゃん
- 好奇心
胎の強みと悩みの傾向
胎の強みは、強い好奇心です。
悩みの傾向は、継続できないことや、実を結ばないことに不甲斐なさを感じやすい事などです。
胎を持っている人は好奇心旺盛で、少しでも気になるものを見つけると、ウキウキしながら色々チャレンジするタイプです。でも、だからこそ持つ悩みでもあります。
- 強い好奇心
- チャレンジ精神
- 継続できなかったり、なかなか実を結ばないことに不甲斐なさを抱えやすい
胎を持った人へのメッセージ
好奇心を満たしたい星なので、結果にこだわり過ぎないことが大切です。
いろいろ挑戦したその先にこそ、見えてくるものがある星です。
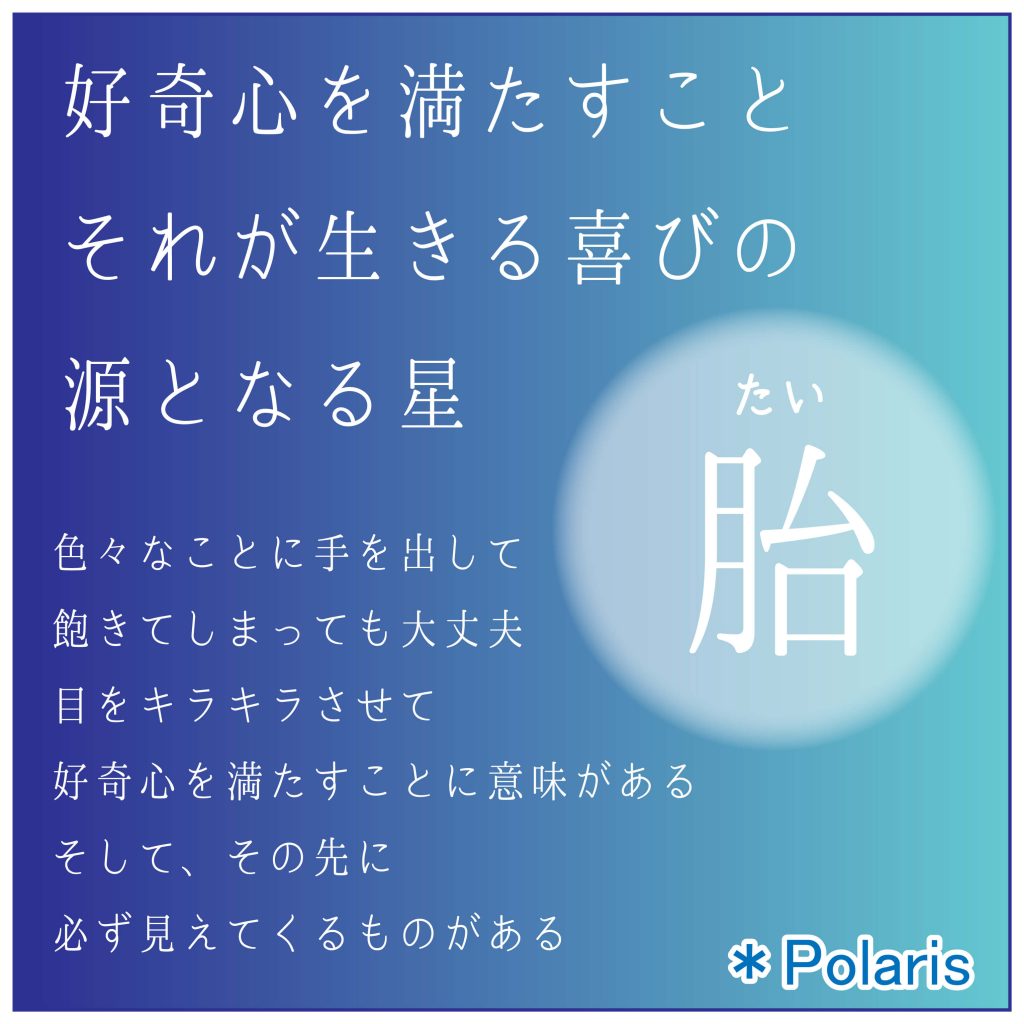
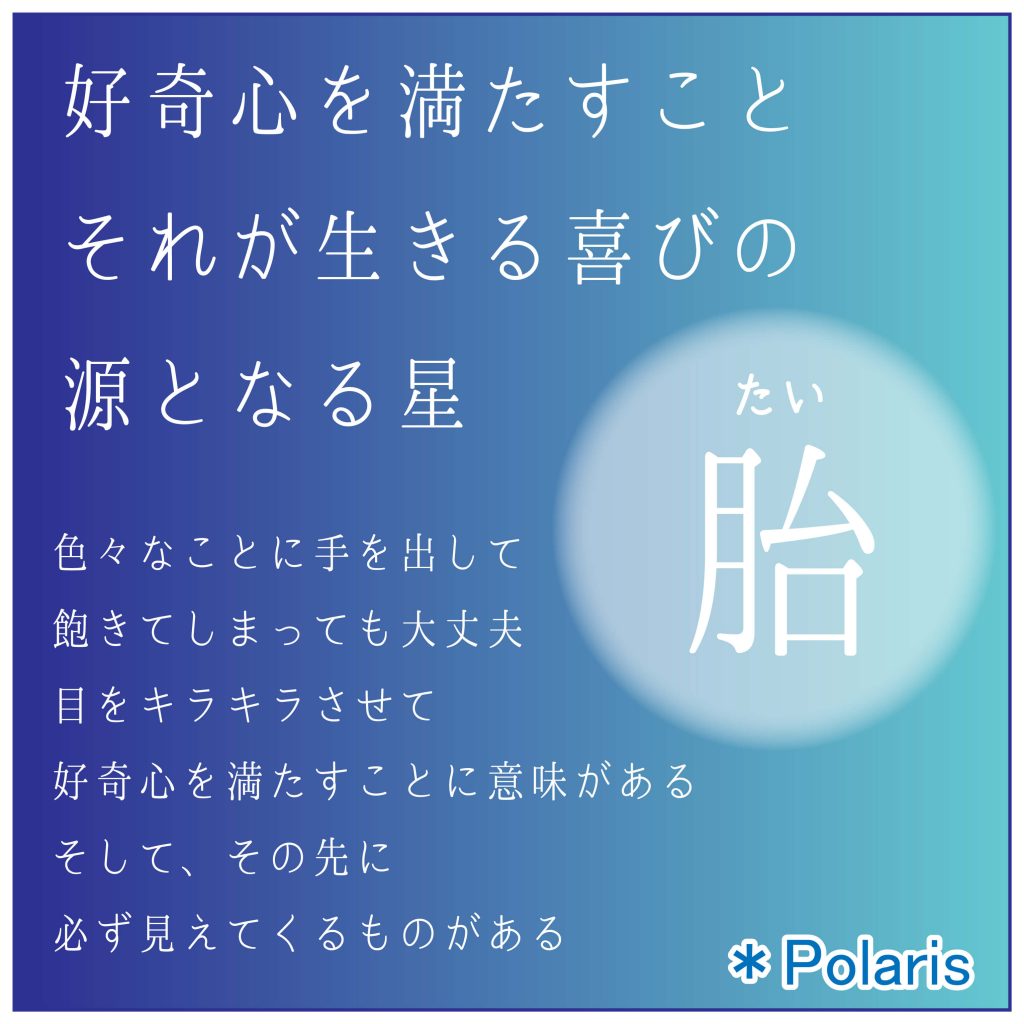
② 養(よう)赤ちゃんの星
養は、生まれたての赤ちゃんの星です。


養が象徴するのもは?
養が象徴するのもは、純粋無垢さです。
産まれたての赤ちゃんは、ただそこにいるだけで、人の心を愛情で満たしてくれます。
無防備な赤ちゃんのつぶらな瞳でじっと見られたら、母性本能を感じたり、少しくすぐったくい気持ちになったりしませんか?
このような性質の養を持っている人は、周囲の庇護欲を掻き立てるようなタイプです。
- 産まれたての赤ちゃん
- 純粋無垢さ
養の強みと悩みの傾向
養の強みは、素直な人柄で可愛がられやすい事です。
悩みの傾向は、嫌でもNoとなかなか言えないことです。
また、養を持った人は、素直で少し弱い印象を与えるために、中にはまやかしの愛を与えて、見返りを求めてくる人もいます。
そういった経験から、人を信じられなくなり、素直に愛情を受け取れない悩みを持つこともあります。
- 素直な人柄
- 人から可愛がられる
- 嫌でもなかなかNoと言えない
- 押しに弱く流されやすい
養を持った人へのメッセージ
本来、愛情に条件はありません。見返りを求める人とは、距離を置くのも一案です。
あとは、受け取るものを自分で選ぶこと、それを受け取る勇気も必要です。そして、受け取ったものを他の誰かへ循環させることも大切です。
また、自分の意志をはっきり伝える意識を持つと尚いいです。
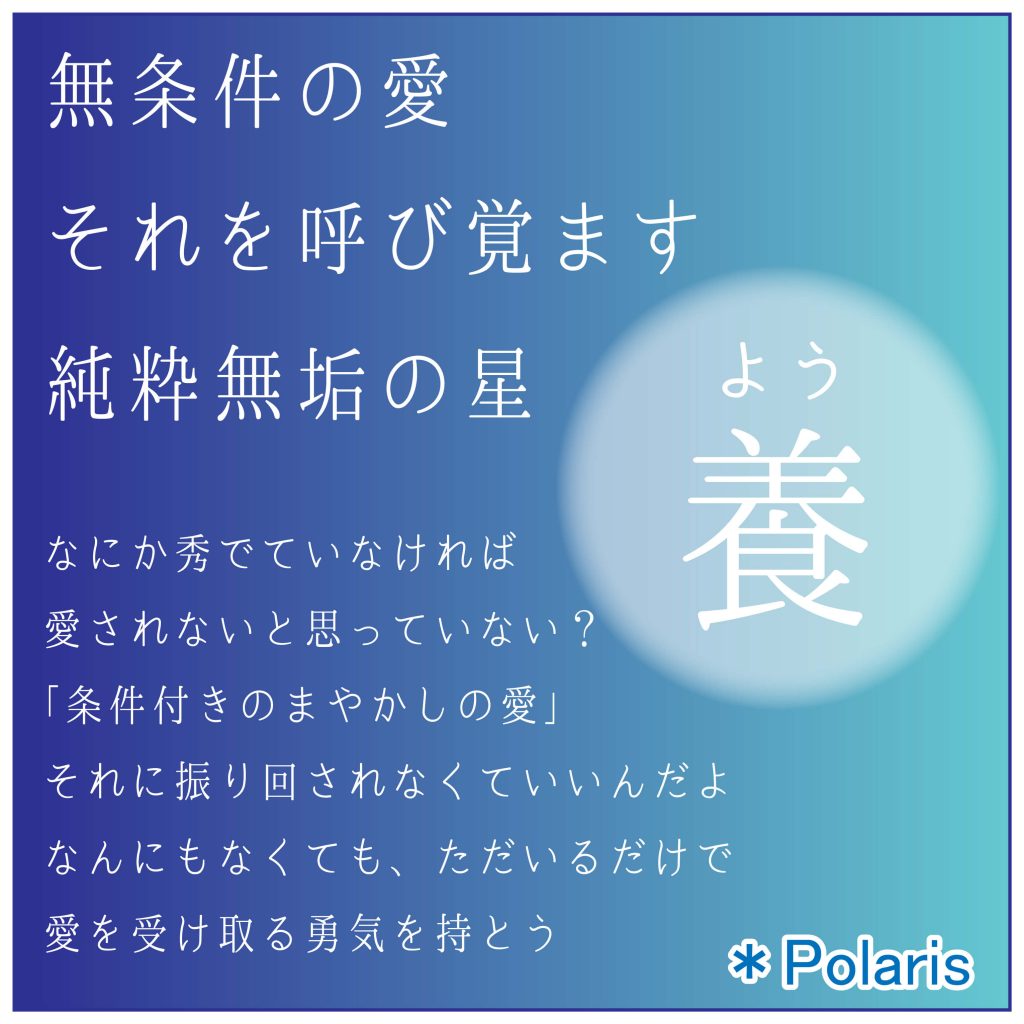
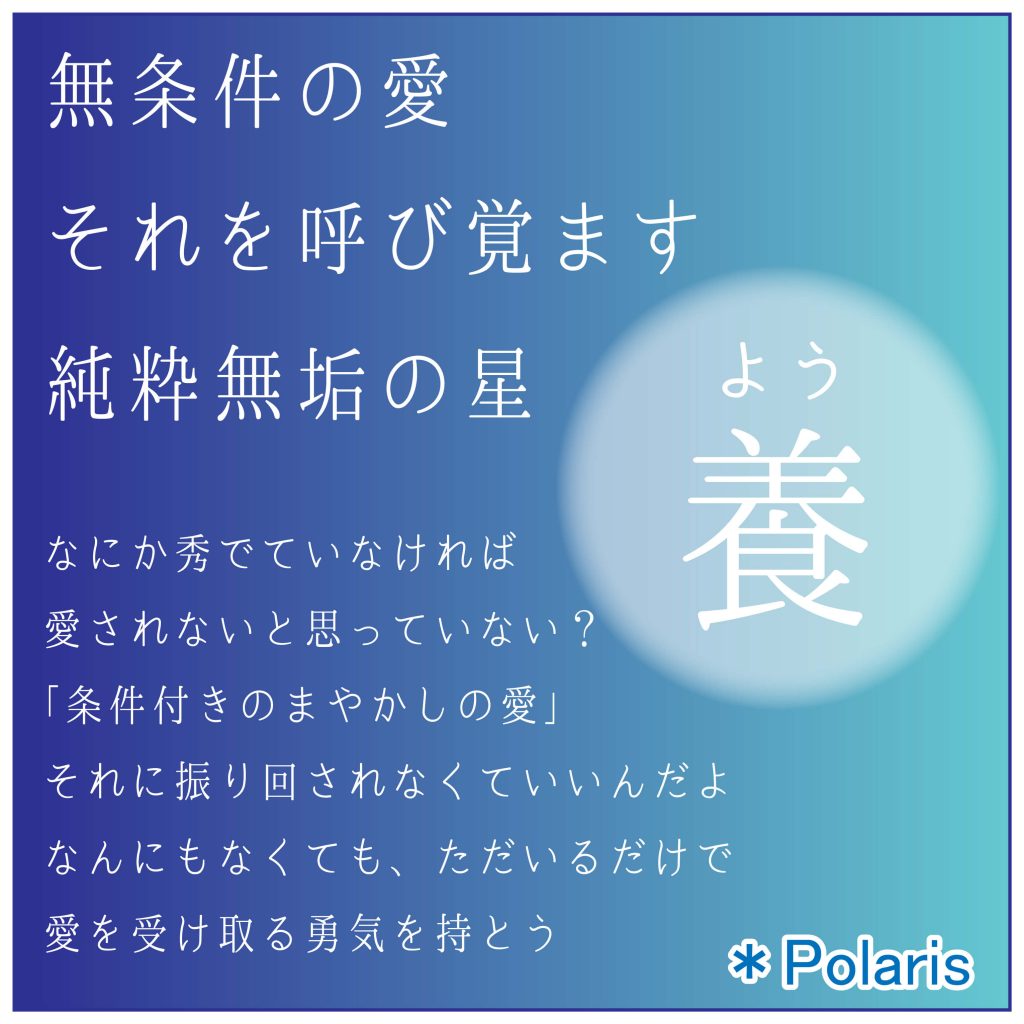
③ 長生(ちょうせい)幼児期の星
長生は、幼児期の星です。


長生が象徴するものは?
長生が象徴するものは、跡取り、親・親族・目上の人からの期待です。
幼児期は、成長するにつれて親の希望である「こうあって欲しい」などの期待をかけられだす年ごろです。
ですが、この時期は無邪気で幼く、期待はされてもまだまだちゃんとは出来ません。失敗という経験を積みながら、成長していく時期です。
このような性質の長生を持った人は、周囲からなにかと期待を向けられやすいタイプです。
- 幼児期
- 跡取り
- 親・親族・目上の人からの期待
長生の強みと悩みの傾向
長生の強みは、周りに誠実な印象を与える事です。
悩みの傾向は、親や職場などで「期待に応えなければ!信頼を裏切ってはいけない」と、プレッシャーを感じる事です。
- 誠実な印象
- 真面目
- プレッシャーを感じやすい
長生を持った人へのメッセージ
長生を持っている人は、長男長女でなくても家を継ぐ人が多いです。また、伝統的なものを受け継ぐ立場になることも多く、跡継ぎの星とも言われています。
しかし、長生を持っていても、なんでも人の期待通りにできる訳ではありません。自分のキャパを超えることは、一人で頑張らず、誰かに助けを頼む事も大切です。
また、家も必ず継がなければならない訳でもありません。大切なのは、何を受け継ぎ、何を後世に繋げて行くのか?という事です。
そして、それは自分の意思で選んで良いのです。
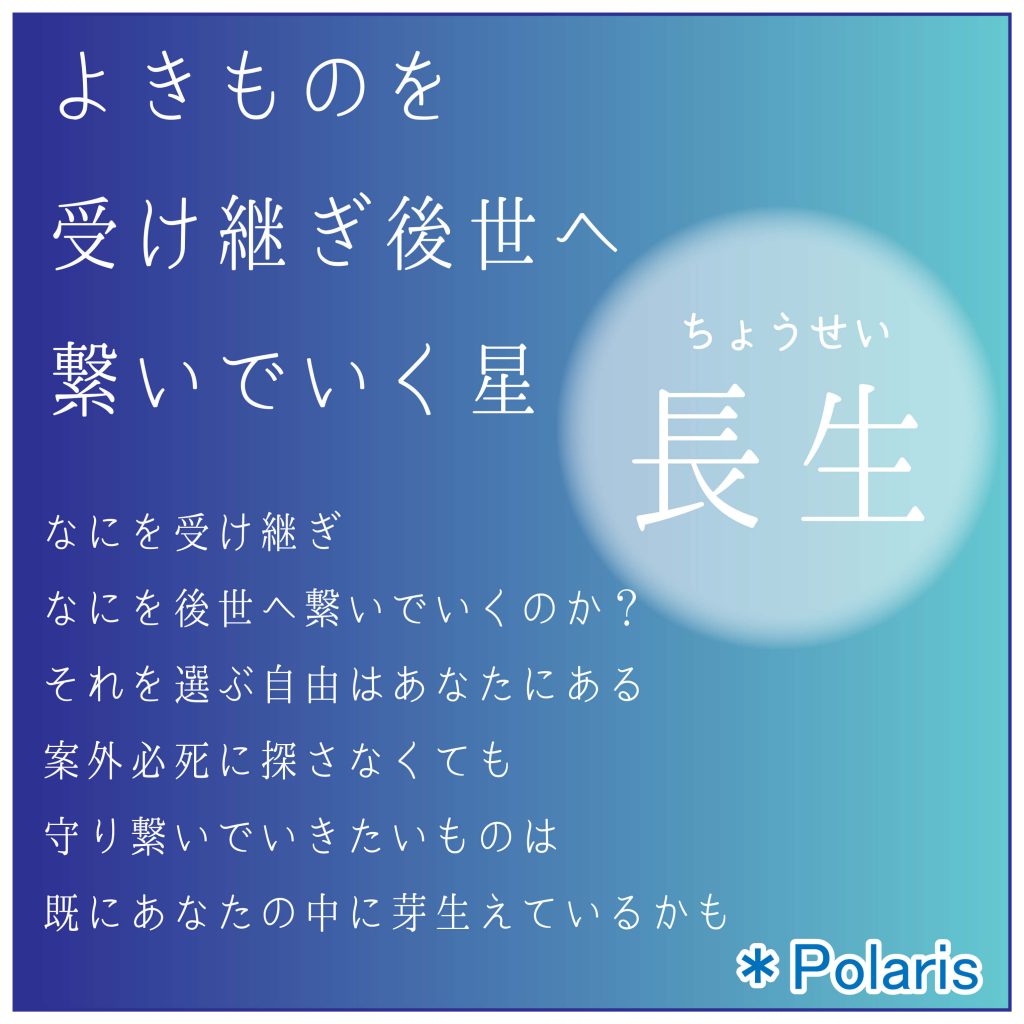
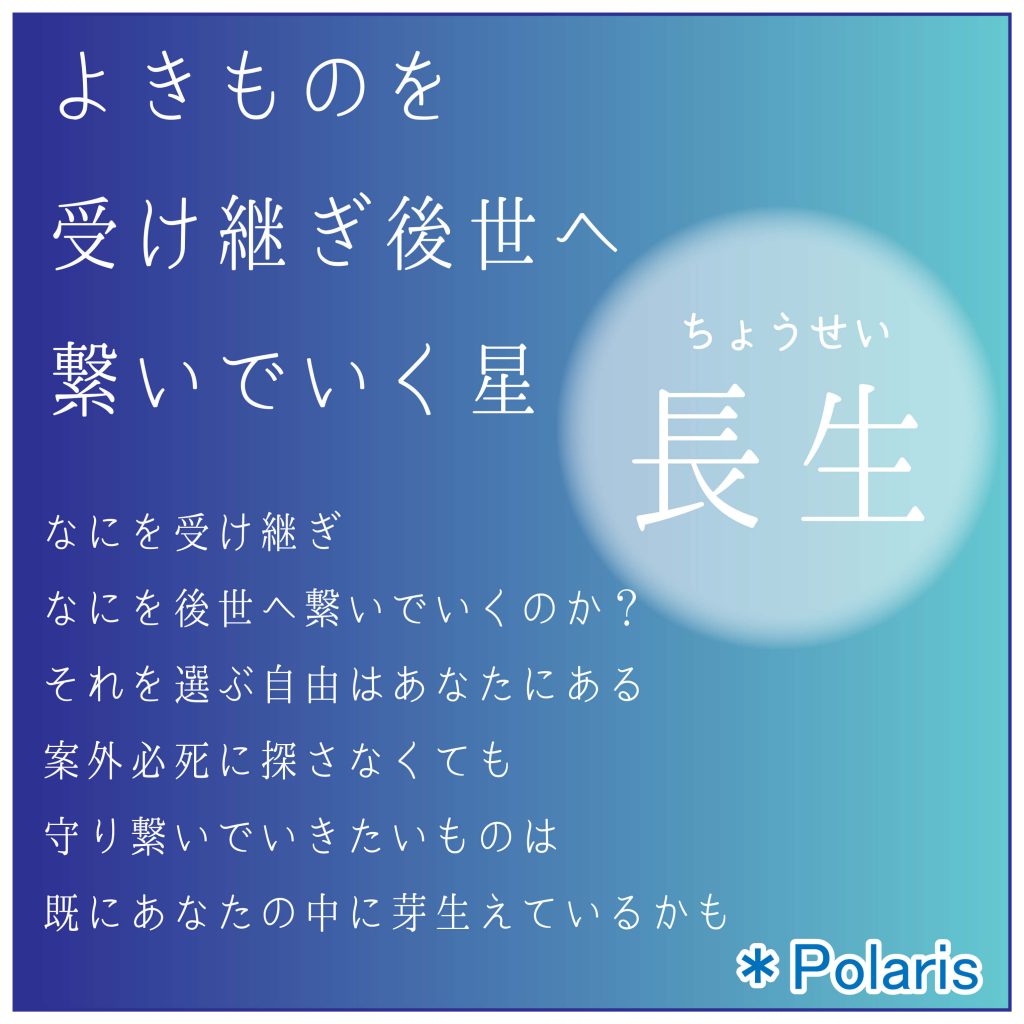
④ 沐浴(もくよく)思春期の星
沐浴は、思春期の星です。


沐浴が象徴するのもは?
沐浴が象徴するのもは、思春期、自分を縛る世界からの開放、自由や夢です。
思春期は多感で、親や自分を取り巻く社会に対しての反抗心も強くなる頃です。
また、現実的な考えを優先するより、自分の理想の世界へ憧れを募らせます。将来の夢が広がっていくのもこの時期です。
このような性質の長生を持った人は、自由奔放な印象を与えるタイプです。
- 思春期
- 自由奔放
- 夢
沐浴の強みと悩みの傾向
沐浴の強みは、常識を破るアイディアや突破力です。
悩みの傾向は、不自由さを感じたり、素直にルールを受け入れられない苦しみです。
- 斬新なアイディア
- 突き進む突破力
- 自由を求めているのに、不自由を感じることが多い
沐浴を持った人へのメッセージ
沐浴を持っている人は、型にハマることが苦手です。また、自由を求め夢見ることが原動力となります。
人間みんなが型にハマってしまうと、この世界は退屈で窮屈になってしまいます。
沐浴の人の自由さは、多くの人が抱えている抑圧の突破口となります。自分らしさを抑圧せず、素直に表現していって欲しいと思います。
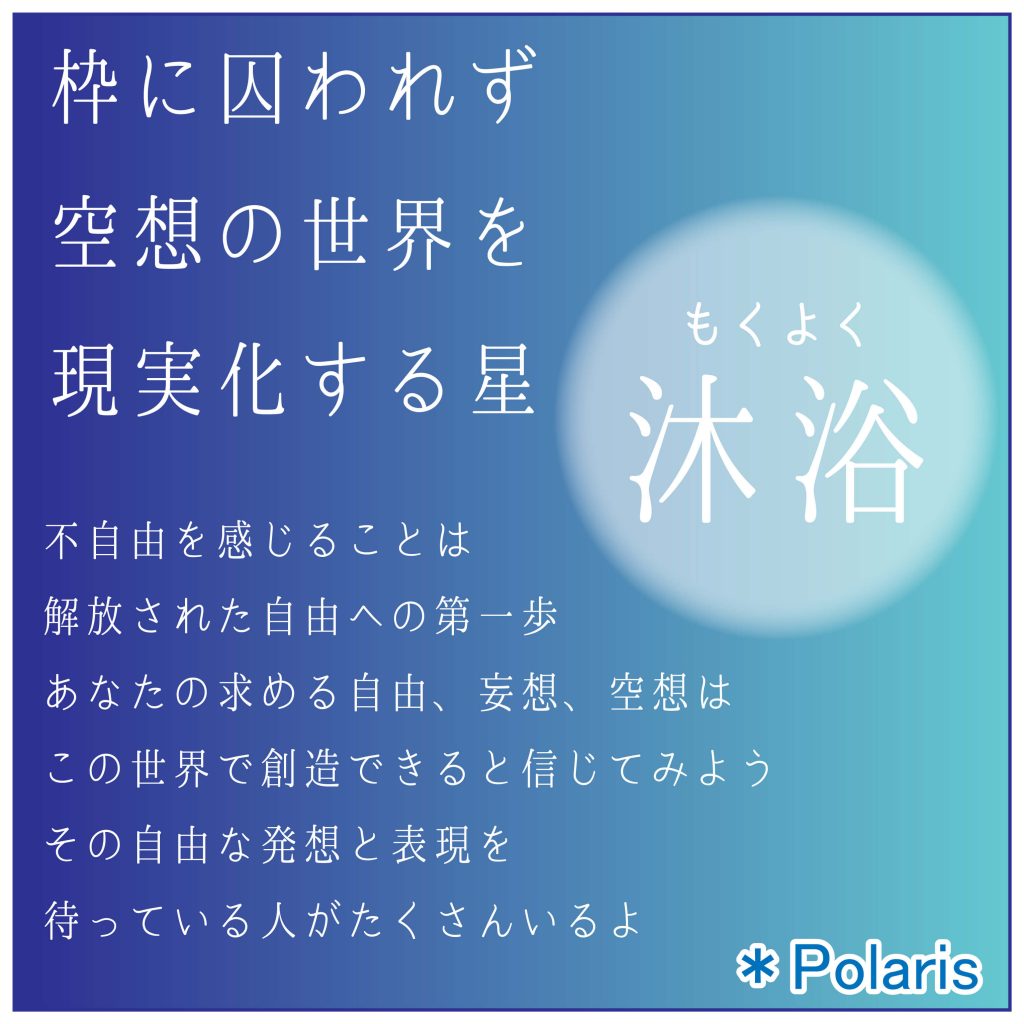
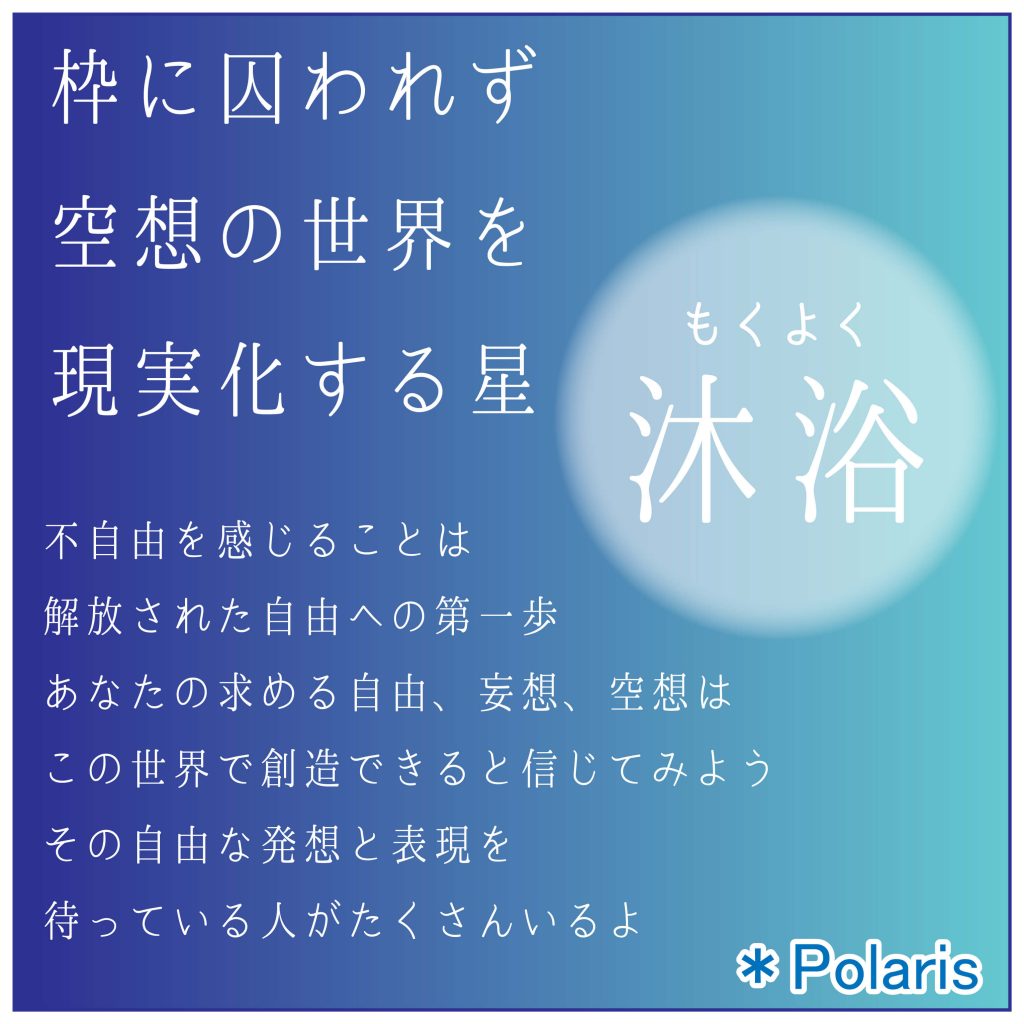
⑤ 冠帯(かんたい)女王様の星(青年期)
冠帯は、女王様の星です。


冠帯が象徴するのもは?
冠帯が象徴するのもは、青年期 、女王、価値のあるものへの賞賛と憧れです。
青年期は、思春期を経て、大人への階段を一歩一歩進んでいる時期です。
持ち物なども、子供っぽいものから卒業し、少し背伸びしたワンランク上のものを求めるようになります。
その背景には「自分とは?」と模索していたり「より良い自分になりたい」という望みがあります。
このような性質の冠帯を持った人は、今の自分より少し背伸びしたいタイプです。
- 青年期
- 女王
- 価値あるものへの称賛
冠帯の強みと悩みの傾向
冠帯の強みは、気高さや人目を引き付ける力です。
悩みの傾向は、目立つことへの抵抗感です。また逆に脚光を浴びることへの執着へと転じることもあります。
- 気高さ
- 華やかさ
- 人目を引き付ける力
- 目立つことへの抵抗感
- 上とは真逆の、脚光への執着
冠帯を持った人へのメッセージ
冠帯を持っている人は、女王気質で華やかさ優雅さを好みます。また、気高い精神を持ちプライドも高いです。
このような気質の人に必要なのは、「本物の女王とは?」と自分に問うことです。
自分の国の女王が、どんな女王だと嬉しいだろうか?自分はそんな人柄なのだろうか?と。
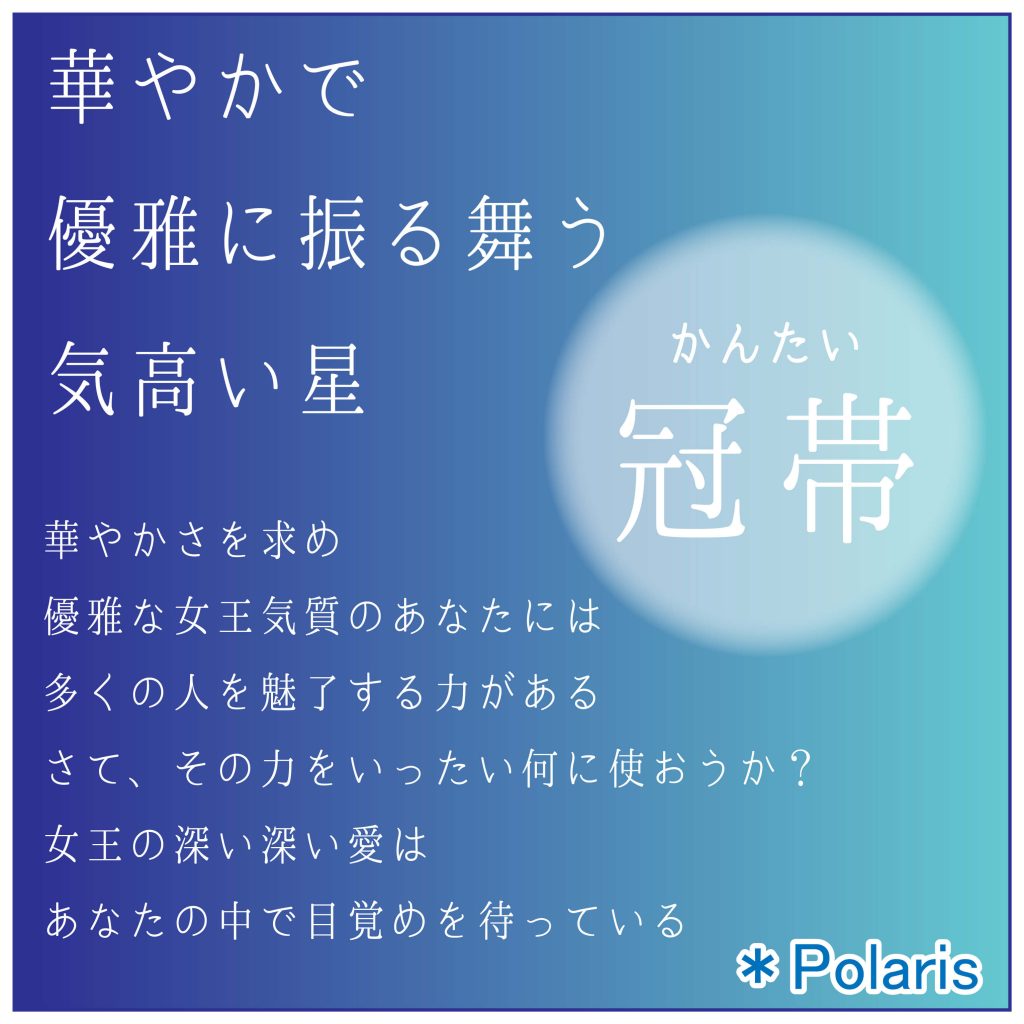
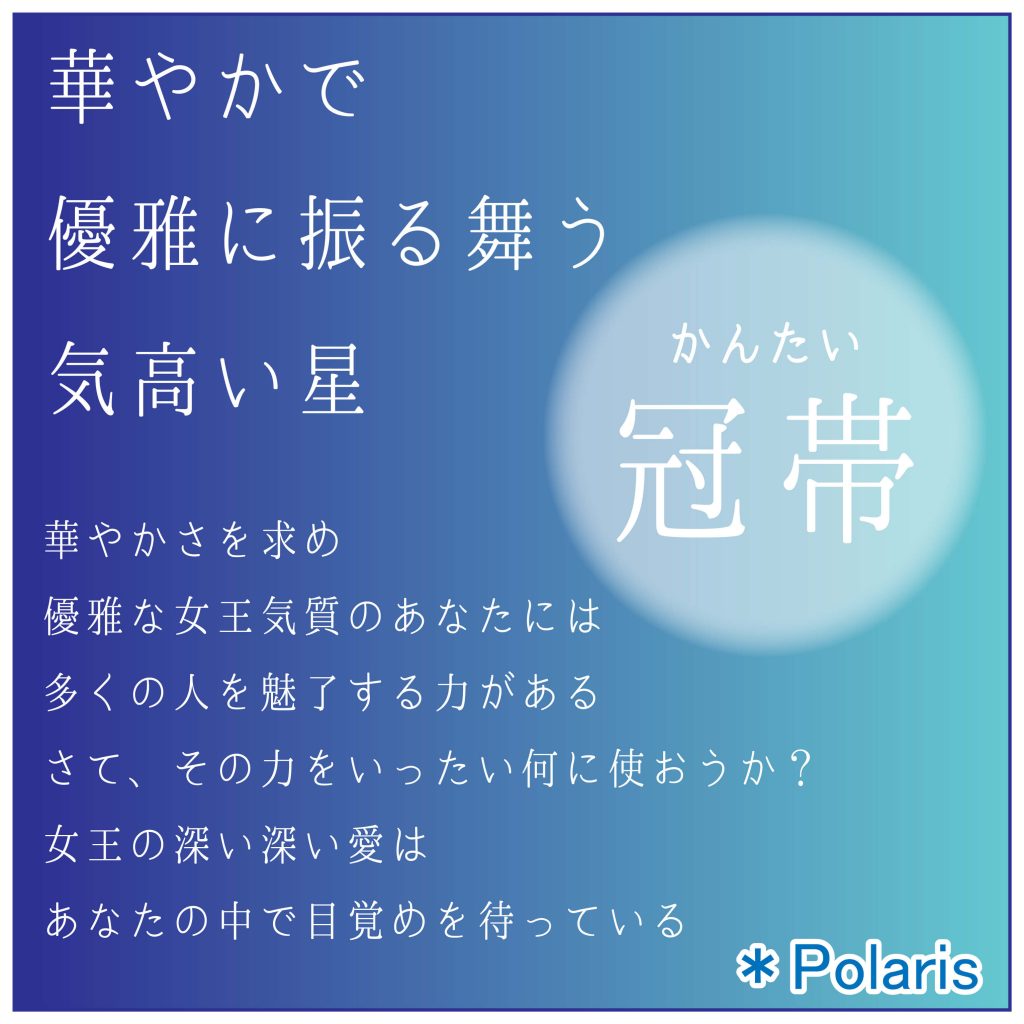
⑥ 建禄(けんろく)王子様の星(成人期)
建禄は、王子様の星です。


建禄が象徴するのもは?
建禄が象徴するのもは、成人期、信念を貫く、王子様などです。
成人すると、誰かの許可がなくとも、自らの判断のみで動くことが可能になります。
ですがまだ、この時期は、自分より経験豊富なサポートする人も身近にいます。例えば、両親や会社の上司など、いざという時に守ってくれる人たちです。
こういった時期だからこそ、結果を恐れずに突き進むことが可能です。
このような性質の建禄を持った人は、純粋に信念を貫こうとするタイプです。
- 成人期
- 信念を貫く
- 王子様
建禄の強みと悩みの傾向
建禄の強みは、力強さや志の高さです。
悩みの傾向は、周囲の反応が心配で、自分が信じる道へ進むことへの抵抗感です。
- 強い好奇心
- チャレンジ精神
- 継続できなかったり、なかなか実を結ばないことに不甲斐なさを抱えやすい
建禄を持った人へのメッセージ
建禄の星の人は、自分が信じることに対して、純粋に進んでいく力があります。しっかりした目的を持った行動なら、周囲を信頼し、前へ突き進む勇気を持ってみましょう。
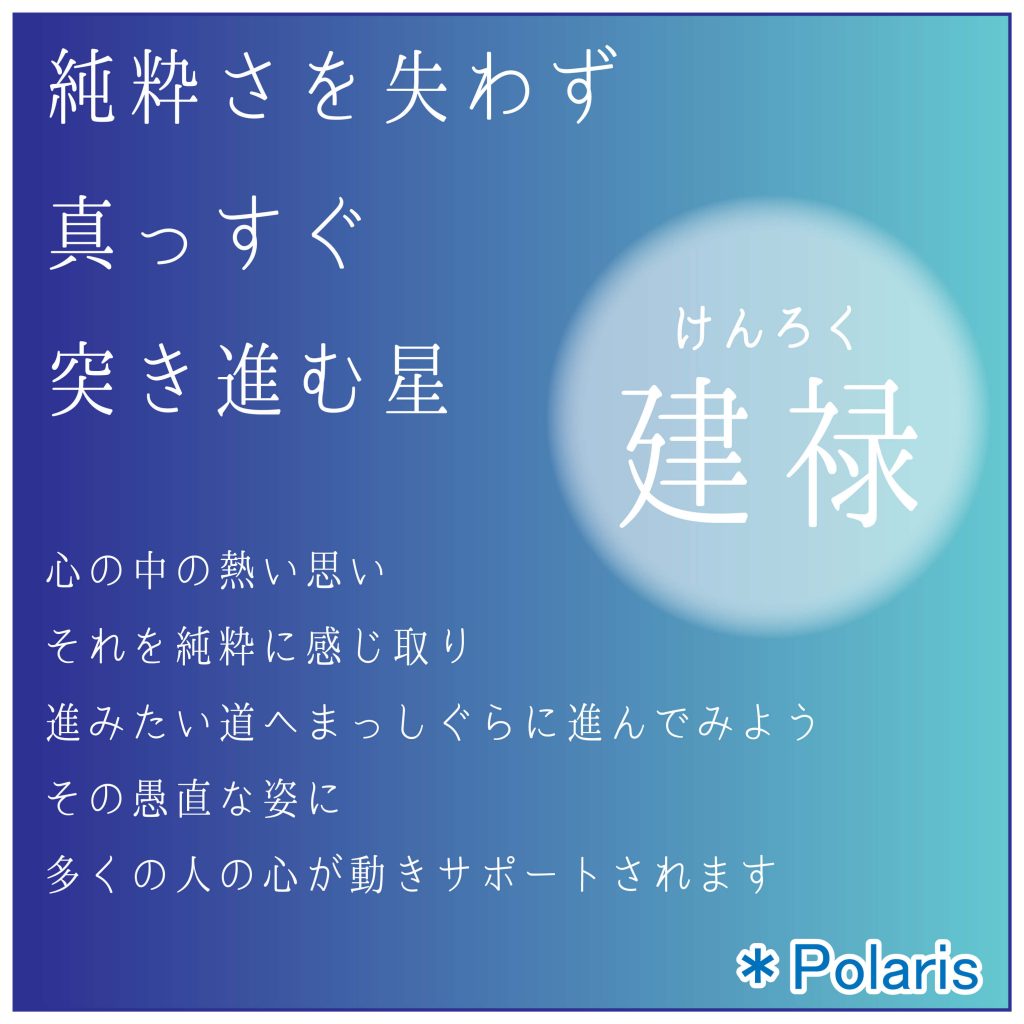
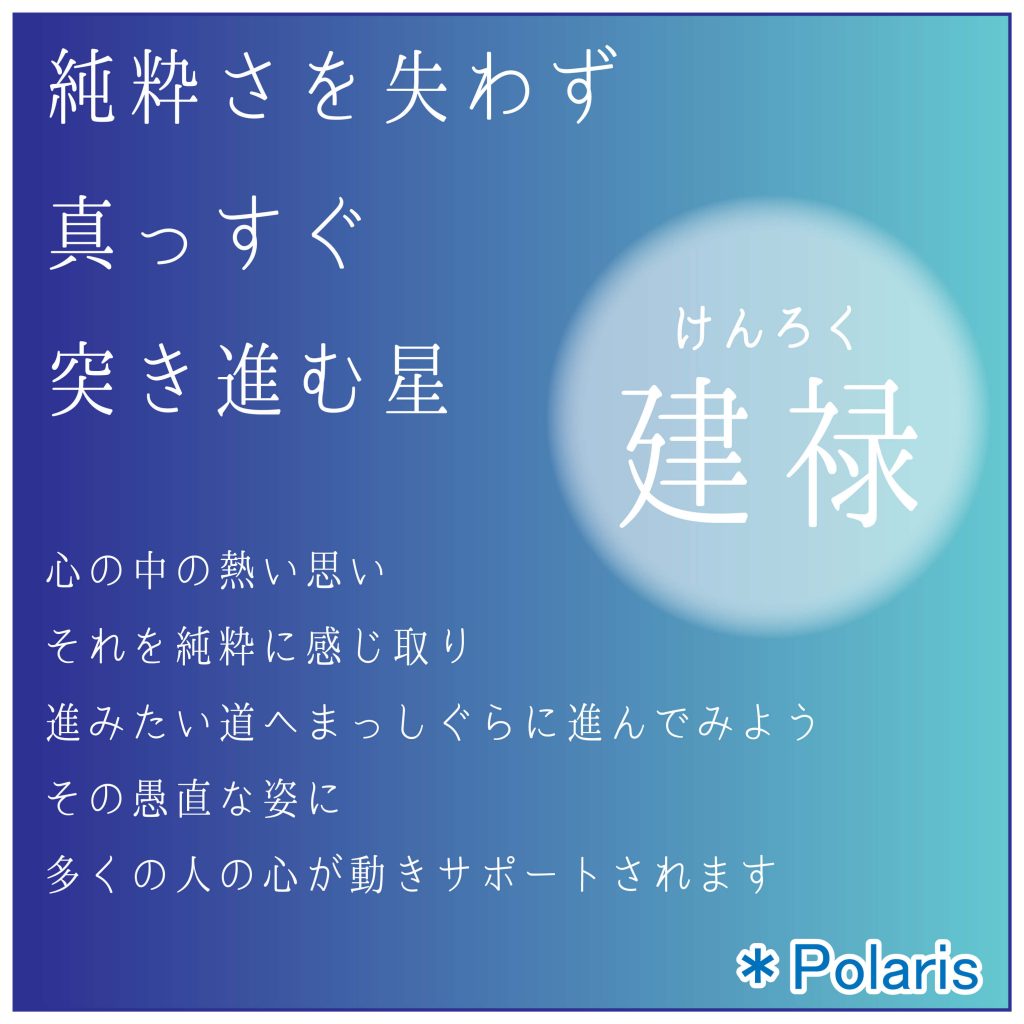
⑦ 帝旺(ていおう)王様の星(壮年期)
帝旺は、王様の星です。


帝旺が象徴するのもは?
帝旺が象徴するのもは、壮年期、統率力、王様などです。
壮年期に入ると、過去に数々の経験をつみ、自信が生まれまれてきます。
思慮深さや実行力も伴い、周囲を導くのに十分な実力を備えています。
この時期は、自分の責任は自分で取ることができ、また周囲へのサポート力も備わっています。
このような性質の帝旺を持った人は、周囲から頼りにされるタイプです。
- 壮年期
- 統率力
- 洞察力
- 王様
帝旺の強みと悩みの傾向
帝旺の強みは、求心力や、適材適所を見分けたりする洞察力です。
悩みの傾向は、実力は十分にあるのに、環境によって能力を持て余して使えなかったりなど、不完全燃焼によるストレスです。
- 求心力
- 洞察力
- 能力の不完全燃焼によるストレス
帝旺を持った人へのメッセージ
帝旺の星を持った人は、周囲の人をまとめて、一つの方向へ導く才能があります。ですが、自分はダメだと卑下していては、誰もついては来てくれません。
かといって、力ずくで人を動かそうとすると暴君となってしまいます。
この力加減は、様々な経験の中から身につけていくものです。経験を糧とする意識を持ちましょう。
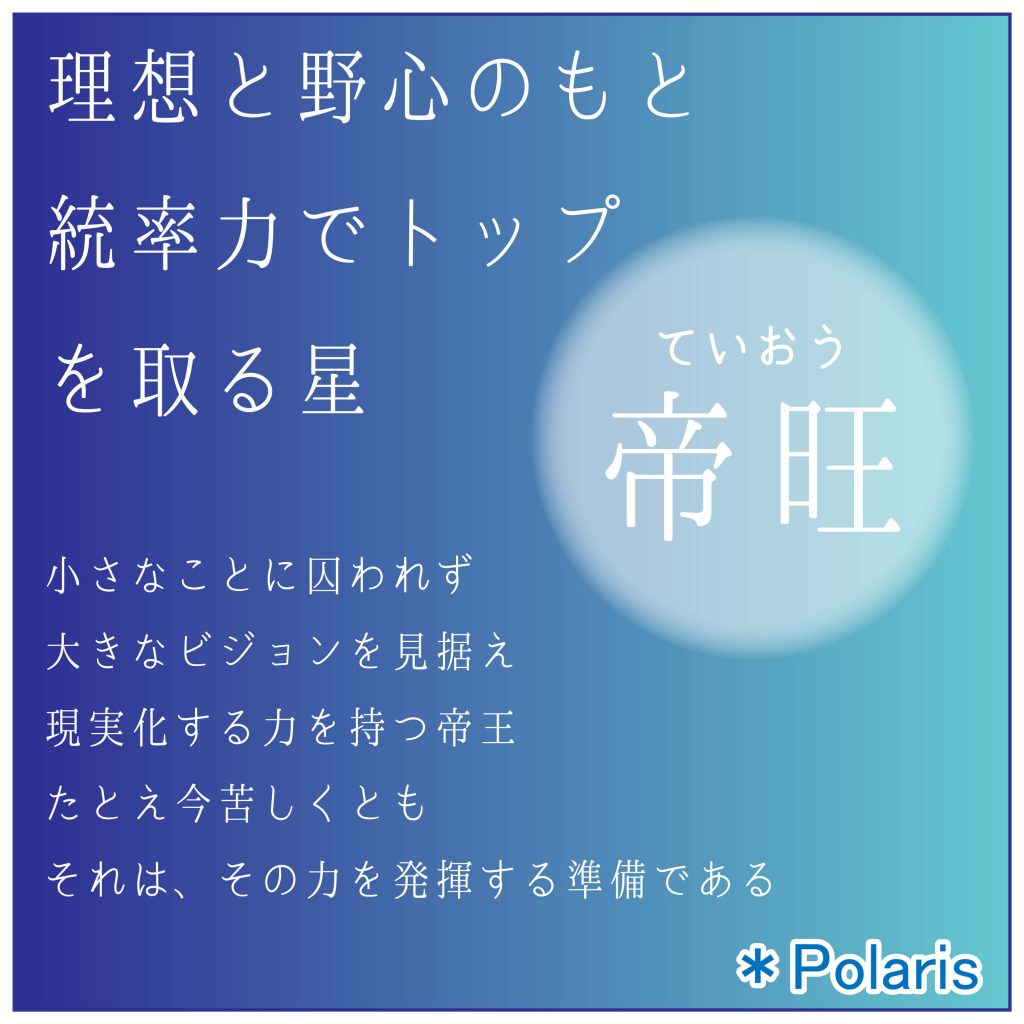
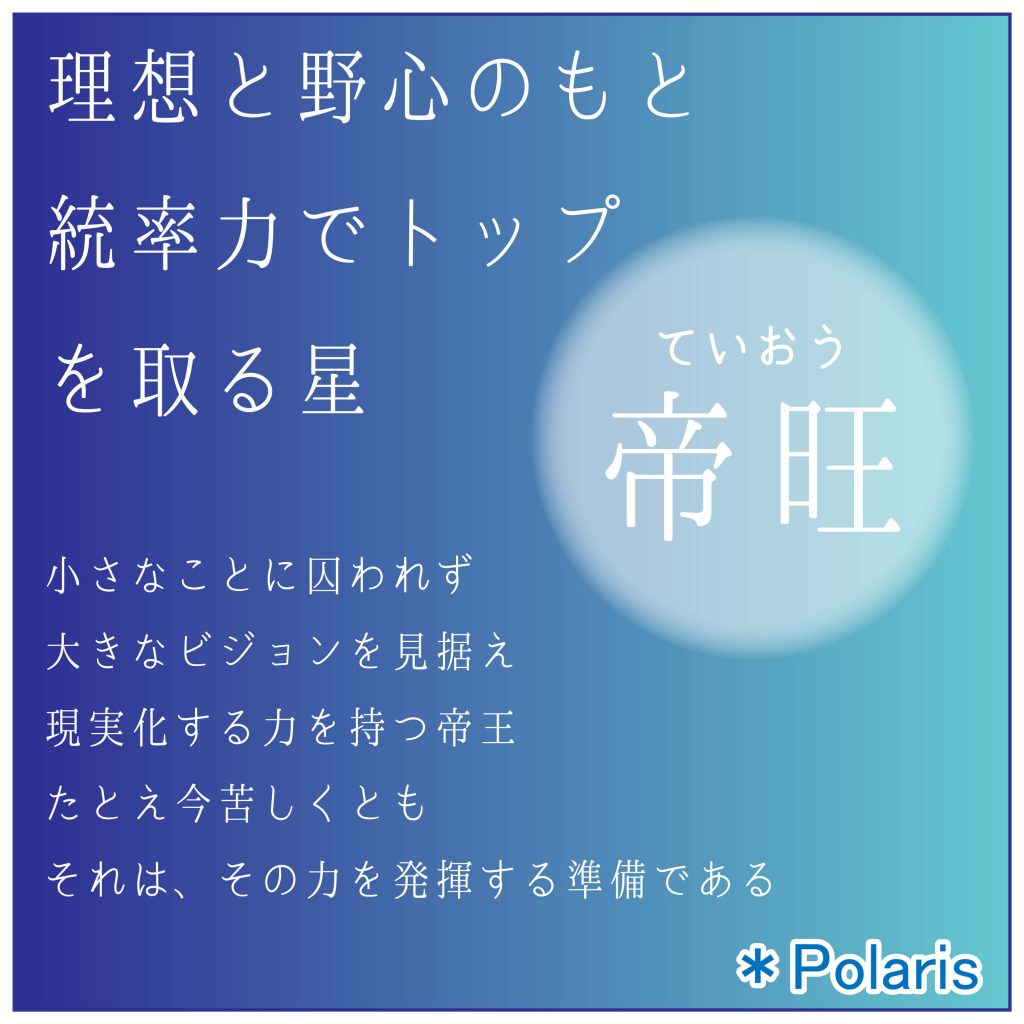
⑧ 衰(すい)長老の星(老年期)
衰は、長老の星です。


衰が象徴するのもは?
衰が象徴するのもは、老年期、智恵、経験などです。
老年期は、全盛期と比べ体力的な衰えを感じ、第一線を退き若い世代に託していく頃です。
体を酷使しての勝負より、智恵をどう活かしていくのか?が重要になってくる時期です。
このような性質の衰を持った人は、熟考してから動くタイプです。
- 老年期
- 経験や知恵
- 長老
衰の強みと悩みの傾向
衰の強みは、落ち着きや博識さです。
悩みの傾向は、衰を持った人は、若くから人より様々な経験することが多く、「どうして自分ばかりこんな経験をするのだろう?」となることです。
- 落ち着き
- 博識さ
- 自分ばかり大変な目に合うと感じる
衰を持った人へのメッセージ
数々の経験は、その経験から知恵を授かるためのものです。
その経験を、自分の肥やしと出来れば、誰よりも頼りにされる人物となります。
また、生き字引のようなあなたの知恵を、自分だけでなく人のために使うことが役割でもあります。
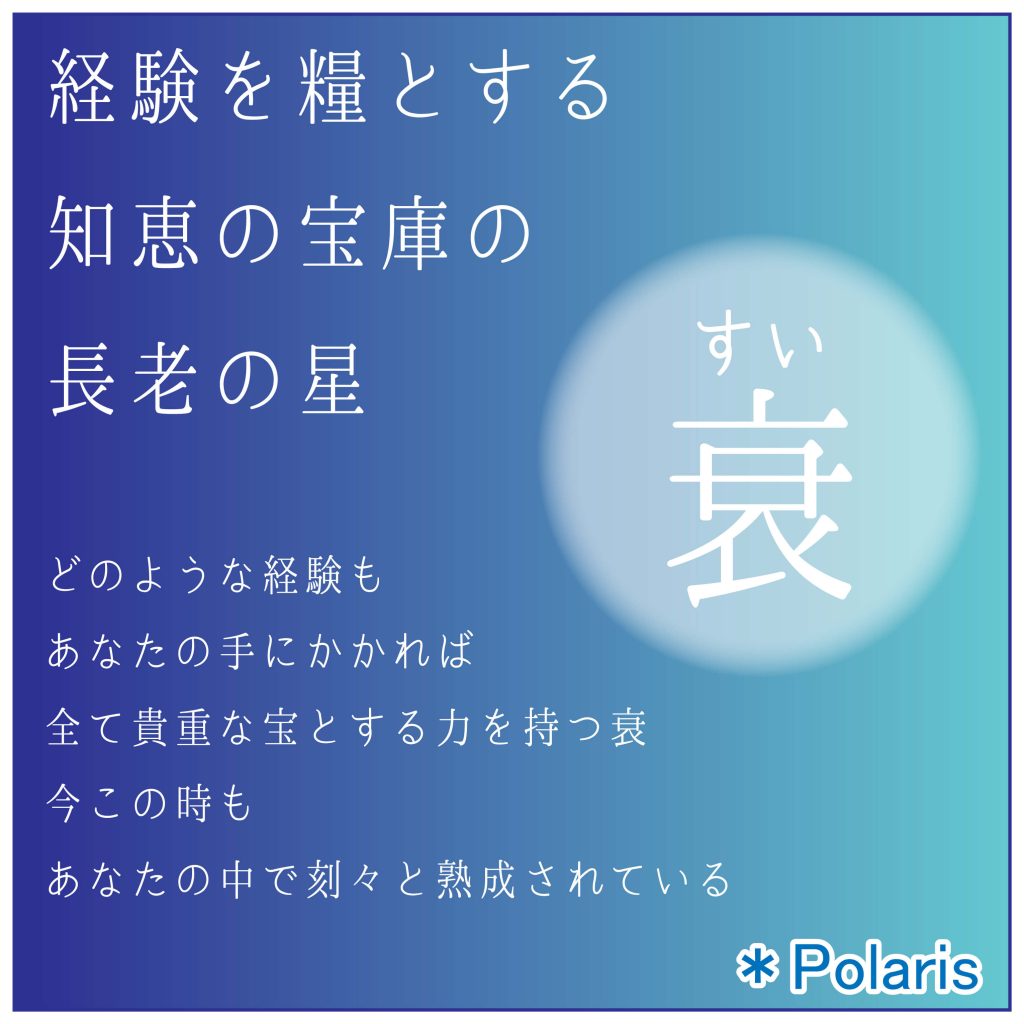
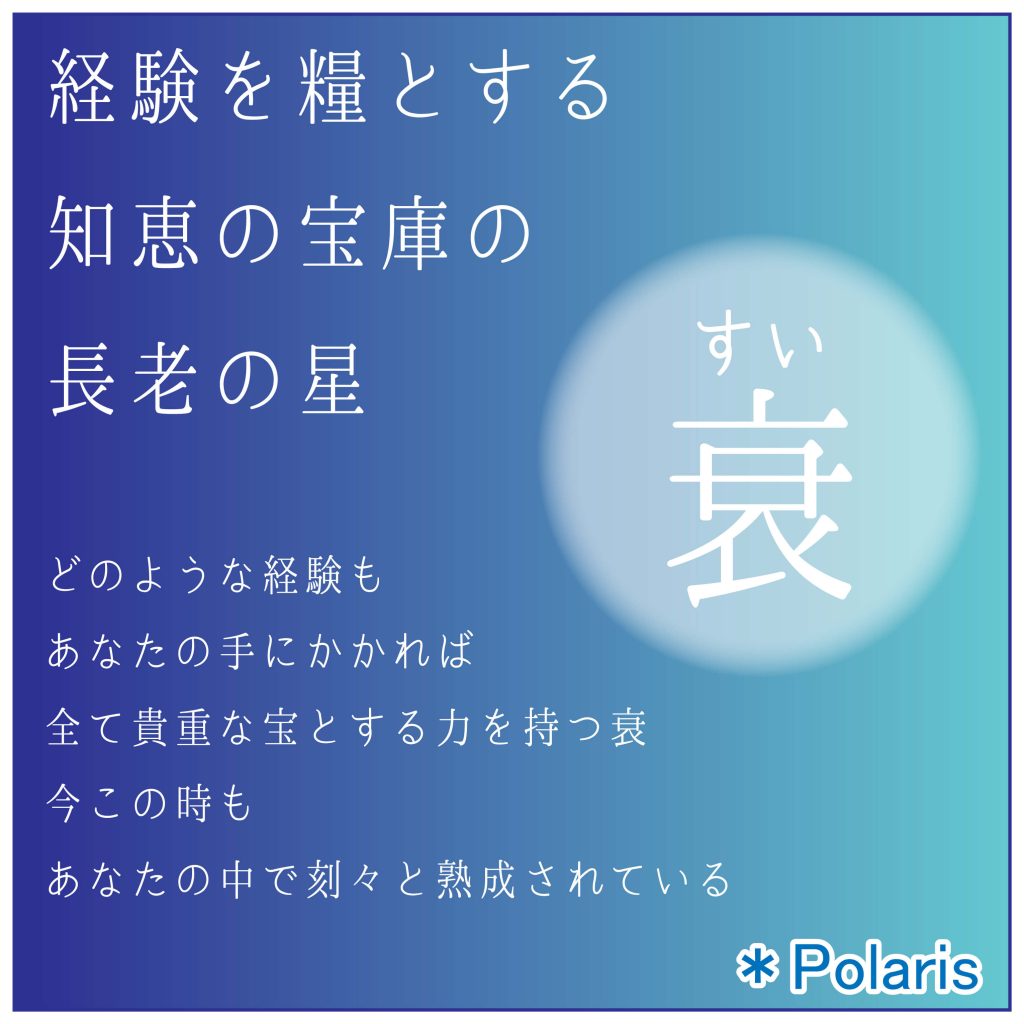
⑨ 病(びょう)肉体が弱った状態の星
病は、肉体が弱った状態を表現した星です。


病が象徴するのもは?
病が象徴するのもは、感受性、芸術などです。
老年期の終盤ともなれば、加齢と共に身体の不調がでてくる頃です。
しかし、思うように身体が動かなくなる半面、これまで意識を向けなかったことを感じるようになります。
そのため、想像力が増し、感受性豊かになるのが老年期の終盤です。
このような性質の病を持った人は、感受性豊かな芸術派タイプです。
- 感受性
- 芸術
病の強みと悩みの傾向
病の強みは、豊かな想像力や表現力です。
悩みの傾向は、豊かな感受性により自分の中に生まれたものを、外へ向かって表現せず持て余すとモヤモヤしてしまいます。
- 豊かな想像力
- 表現力
- 継続できなかったり、なかなか実を結ばないことに不甲斐なさを抱えやすい
病を持った人へのメッセージ
一長一短に表現できないかも知れませんが、その感覚を自分の中に閉じ込めないでください。
外に向かって表現する、自分なりの方法で解放すれば、精神的充足感が得られます。
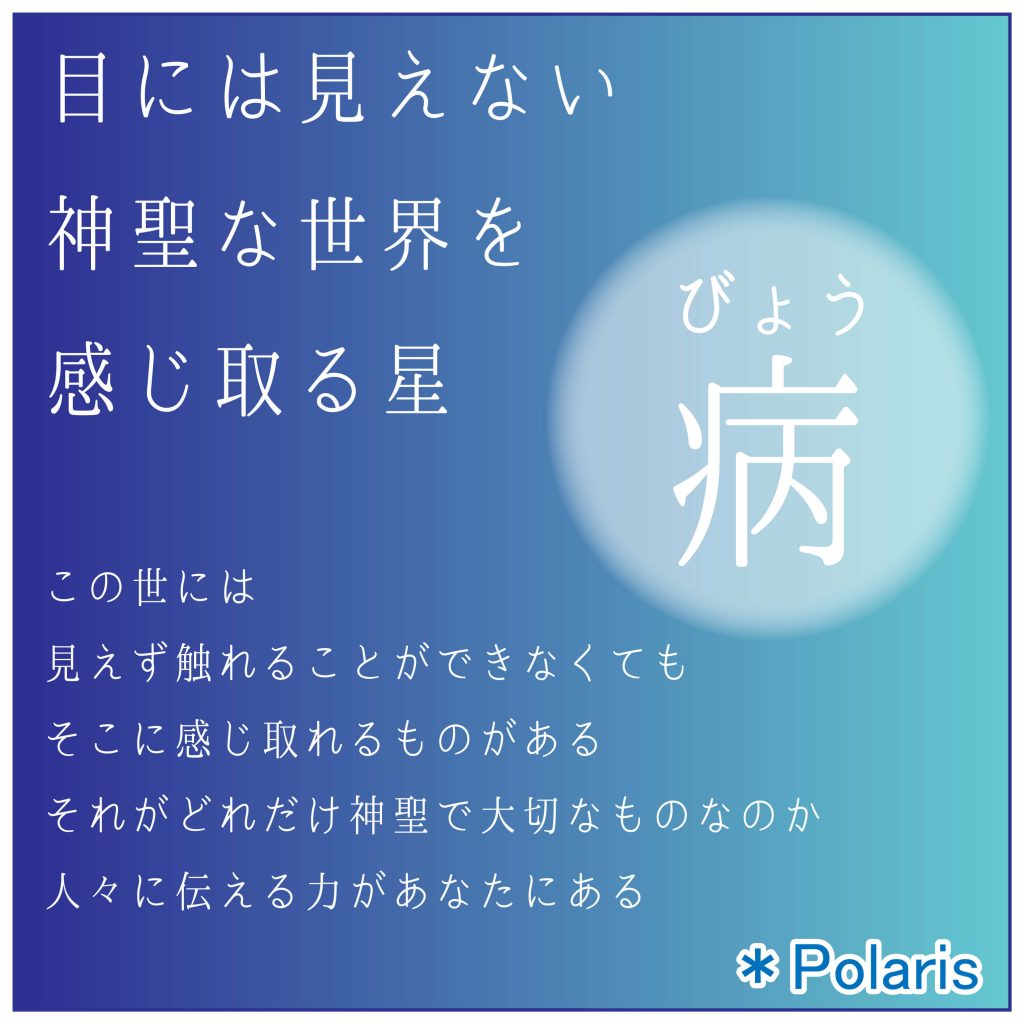
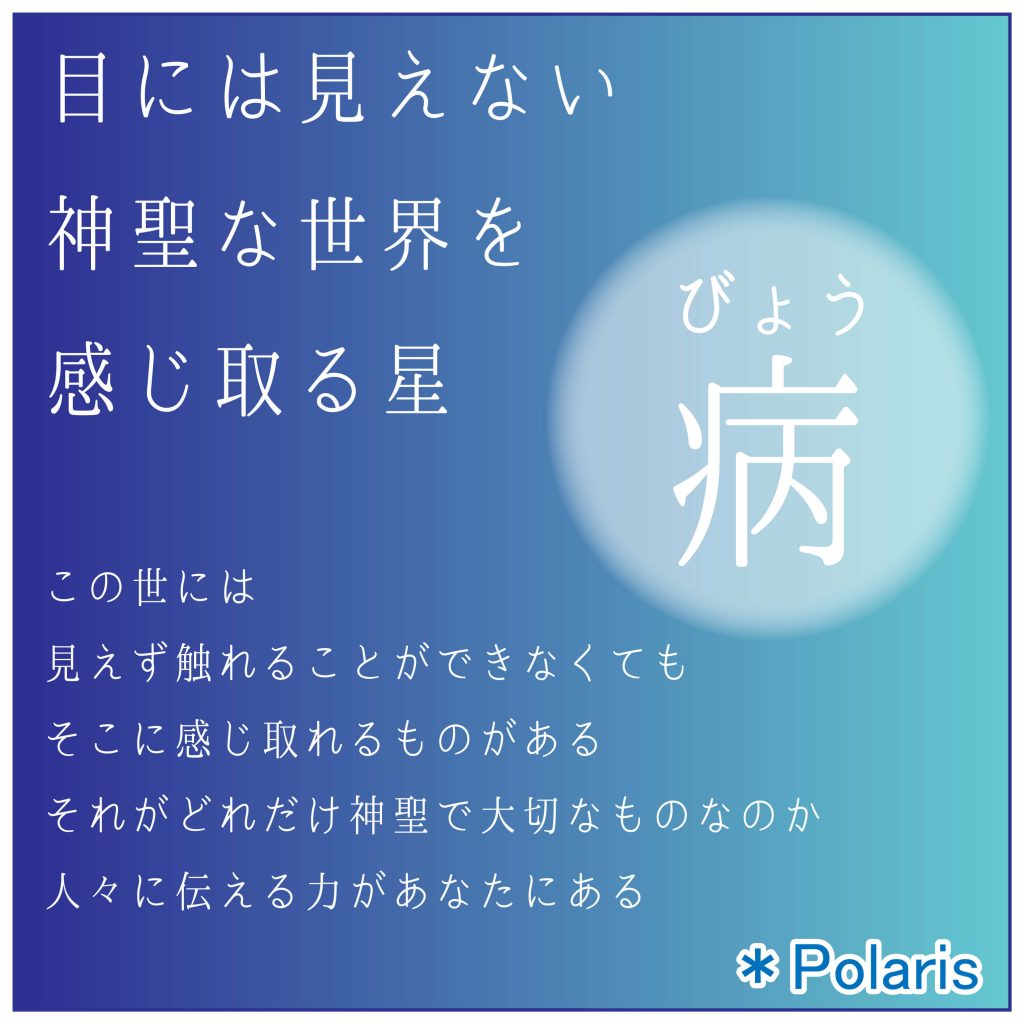
⑩ 死(し)死を迎えた状態の星
死は、死を迎えた状態を表現した星です。


死が象徴するのもは?
死が象徴するのもは、第六感、直観力、ひらめきなどです。
人が死を迎えると、魂の器である肉体の機能が停止し、魂と肉体が分離されます。
肉体はこの世にあり、魂は目に見えない世界へ移行している段階です。
つまり、この世とあの世、両方の世界に存在していることになります。
このような性質の星を持った人は、第六感が働くタイプです。
- 第六感
- 直観力
- ひらめき
死の強みと悩みの傾向
死の強みは、感覚が鋭いこと、嘘を見抜く力などです。
悩みの傾向は、感覚が鋭いために妙な胸騒ぎがあったり、予知夢や感じたくないものまで感じてしまうことです。
- 鋭い感覚
- 嘘を見抜く力
- 胸騒ぎを感じやすい
死を持った人へのメッセージ
死の星を持っている人でも、感覚を閉じ、直観力や見抜く力を使わない人もいます。
しかし本来は、本質を見ることを得意としています。
なぜなら死は、「表と裏」両方の世界に存在し、両方の視点から物事を見れる星だからです。
千里眼とも言える、見る力を大切にして欲しいです。
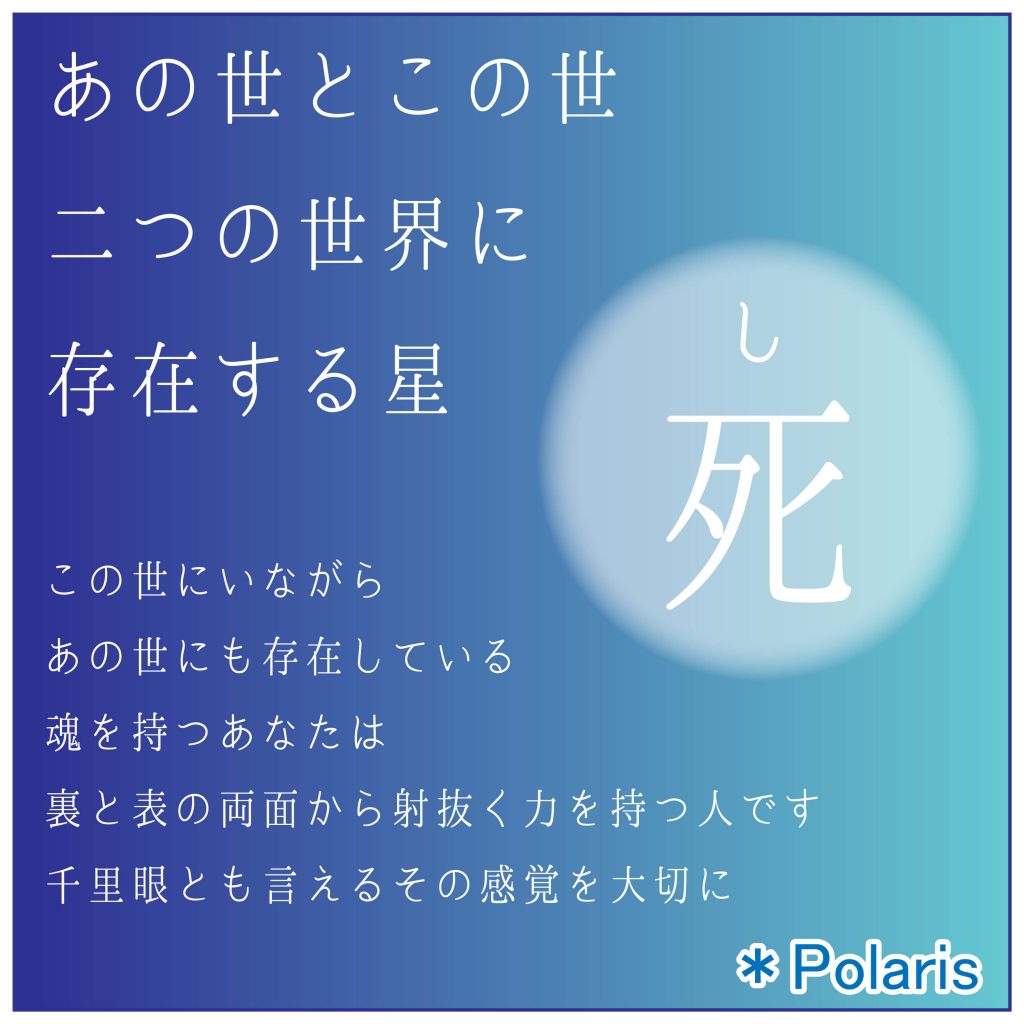
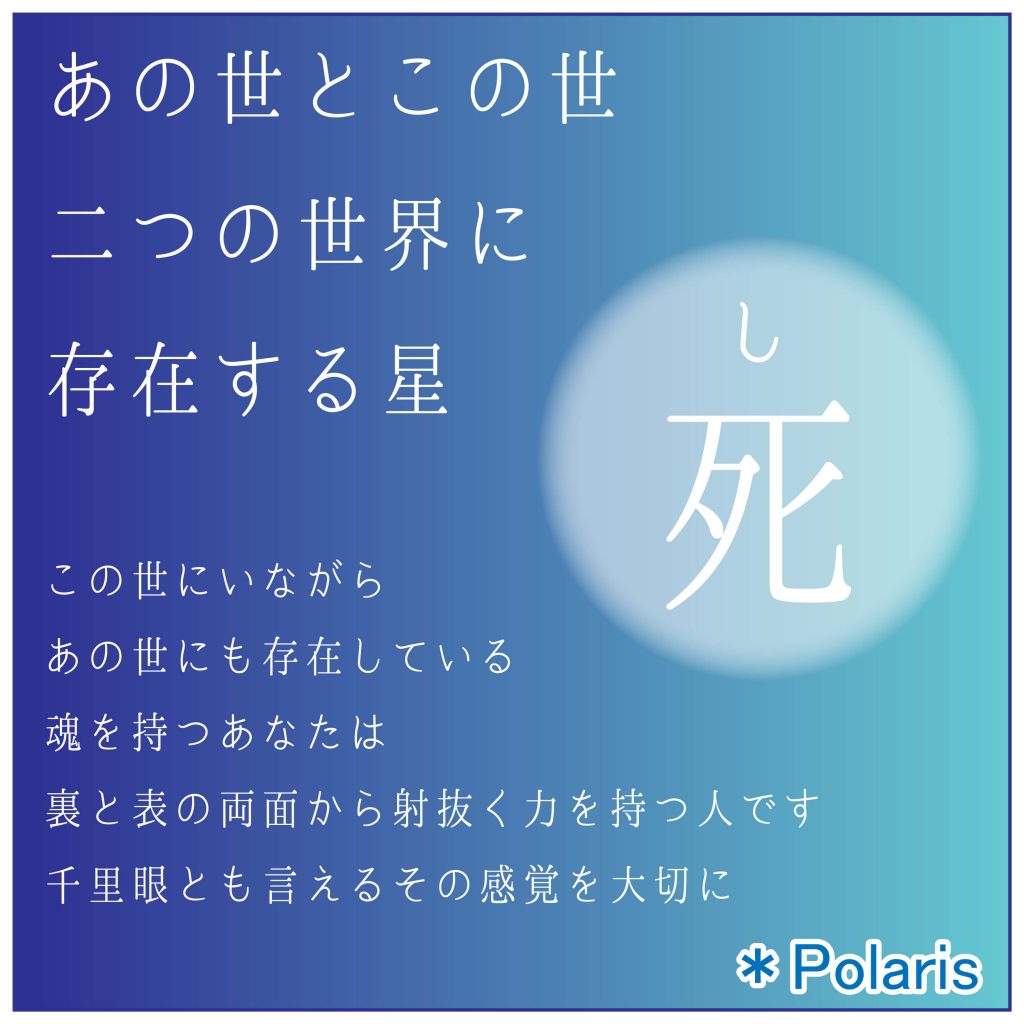
⑪ 墓(ぼ)供養されあの世へ旅立つ準備をした星
墓は、供養されあの世へ旅立つ準備をした状態の星です。


墓が象徴するのもは?
墓が象徴するのもは、探求心、マニアックなどです。
肉体が埋葬され、供養された魂は、この世とあの世の中間の世界から、あの世へと旅立とうとしています。
あの世に着くまでは、たった一人で自分を見つめながらの旅路です。
このような性質の墓を持った人は、マニアックで変わり者なタイプです。
- 探求心
- マニアック
- 学者肌
墓の強みと悩みの傾向
墓の強みは、粘り強さや、探求することが得意なところです。
悩みの傾向は、マニアック過ぎて孤立したり、探求心が執着に替わったり、収集癖で部屋に物があふれやすいなどです。
- 粘り強さ
- 探求心
- 孤立
- 執着
- 収集癖
墓を持った人へのメッセージ
墓の星を持った人は、コツコツ探求することが得意です。その力を自分が好きと感じることに向けましょう。
また、マニアックな自分をオープンにした方が孤立しにくく、周囲にも良い影響を与えます。マニアックな人の活躍で、発展している世界も数多くありますから。
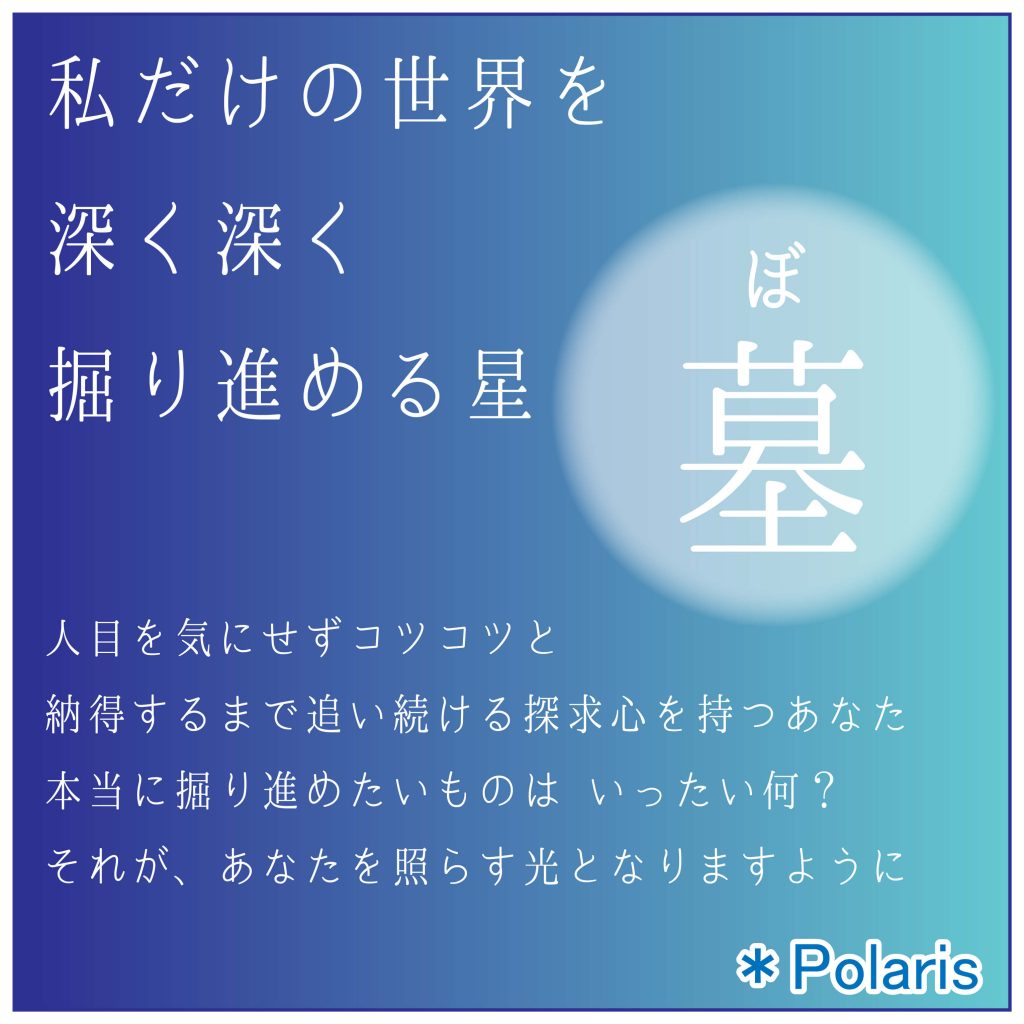
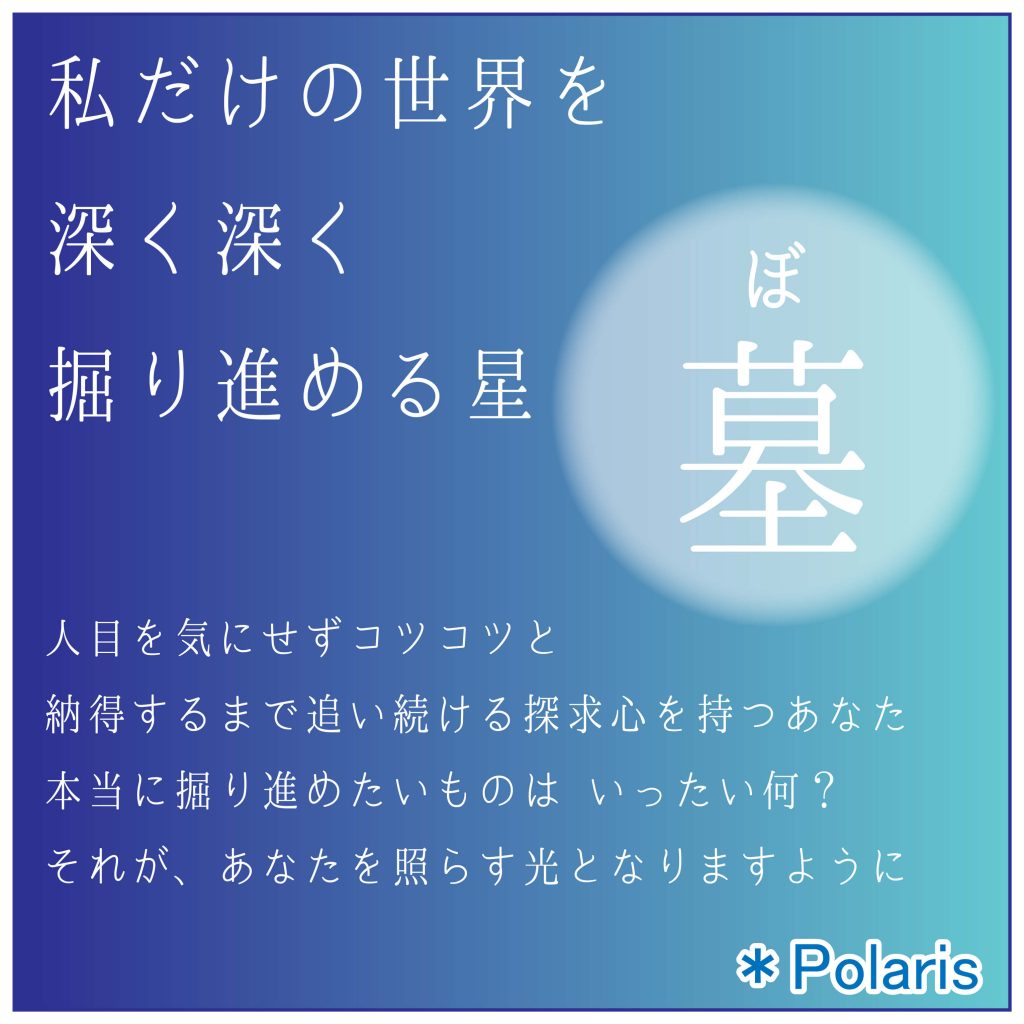
⑫ 絶(ぜつ)あの世の魂の星
絶は、あの世の魂の星です。


絶が象徴するのもは?
絶が象徴するのもは、孤独、天才肌、デリケートなどです。
亡くなってからの旅路を終え、無事あの世へ着いた魂の状態です。
もう今は、人間としての活動である食事や睡眠などを取る必要はありません。その一つ一つにかけがえのなさを感じ、人として生きていた日々を懐かしんでいることでしょう。
このような性質の絶を持った人は、小さなことで一喜一憂するタイプです。
- 孤独
- 天才肌
- デリケート
絶の強みと悩みの傾向
絶の強みは、些細な変化を感じたり、きめ細やかな気配りが出来るところです。
悩みの傾向は、、小さなことが気になり過ぎたり、多感過ぎて肉体的にも精神的にも疲れてしまいやすいことです。
- 変化に気づきやすい
- きめ細やかな気配り
- 些細なことが気になる
- 多感すぎて疲れやすい
絶を持った人へのメッセージ
自分が人よりも繊細で多感であることを知り、その繊細さをどこに向けたいのか?ということを意識することが大切です。
その繊細さで作り上げたものは、きっと素晴らしいものとなるはずです。
また、繊細な感覚で見て感じたことを、恥ずかしがらず周囲に伝えてみましょう。
その感覚に触れた人たちは、見過ごしている「本当は大切なもの」に気づくきっかけとなるはずです。
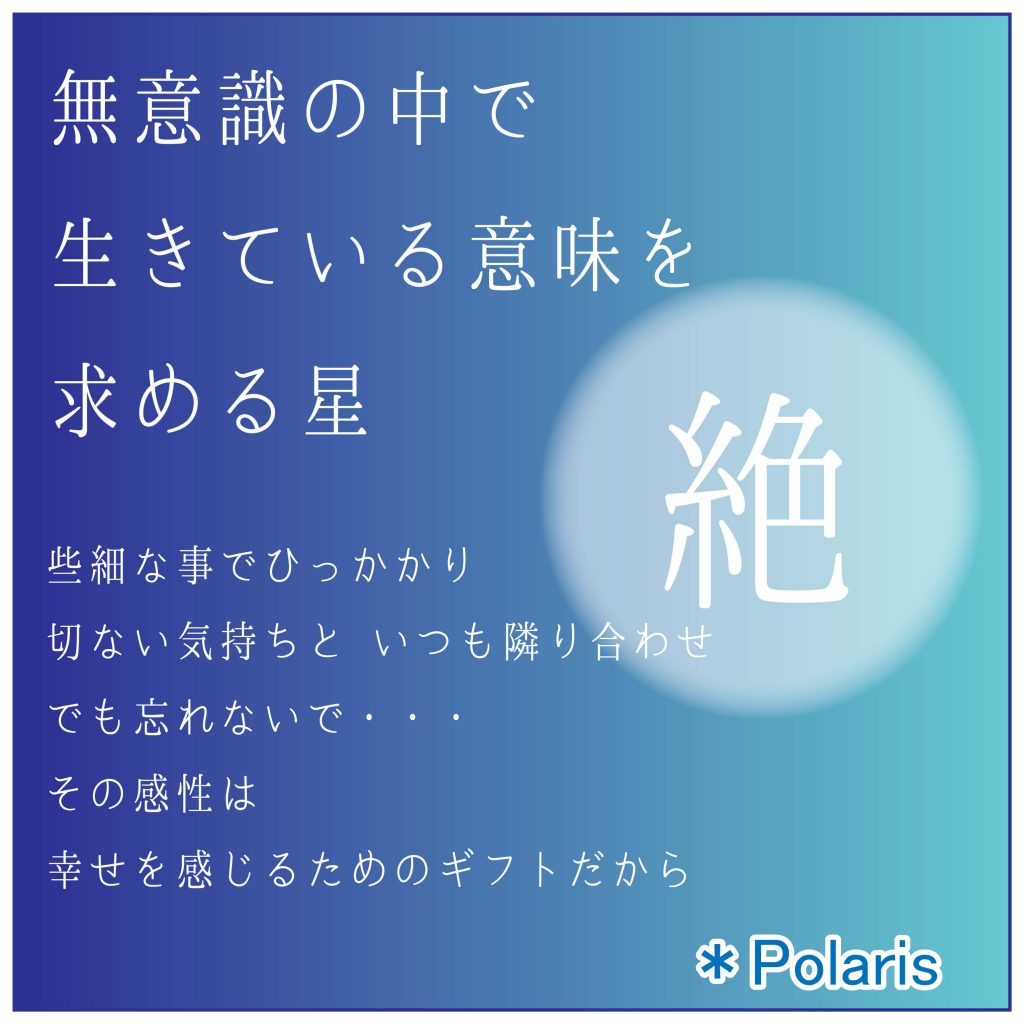
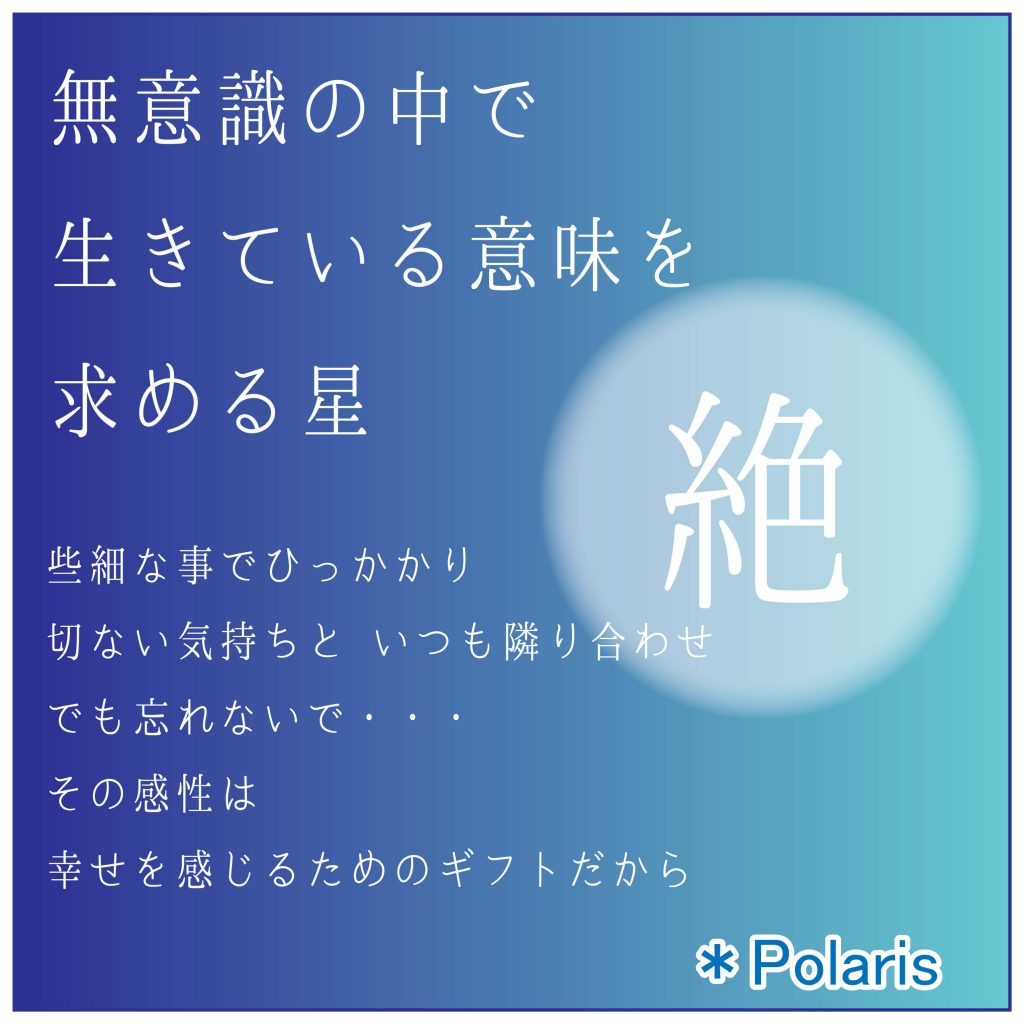
以上、十二運星の星の特徴と、その星を持った人へのメッセージをお伝えしました。
- 十二運星が意味するもの
- 十二運星から分かる事
- 各星の具体的な特徴
- 各星を持った人へのメッセージ
十二運星について、もっと詳しく知りたい場合は下の記事をご覧ください。
こちらの記事は、萬年歴で十二運星を出す方法を紹介しています。
お読みいただき、ありがとうございました。次回記事にてお会いしましょう。

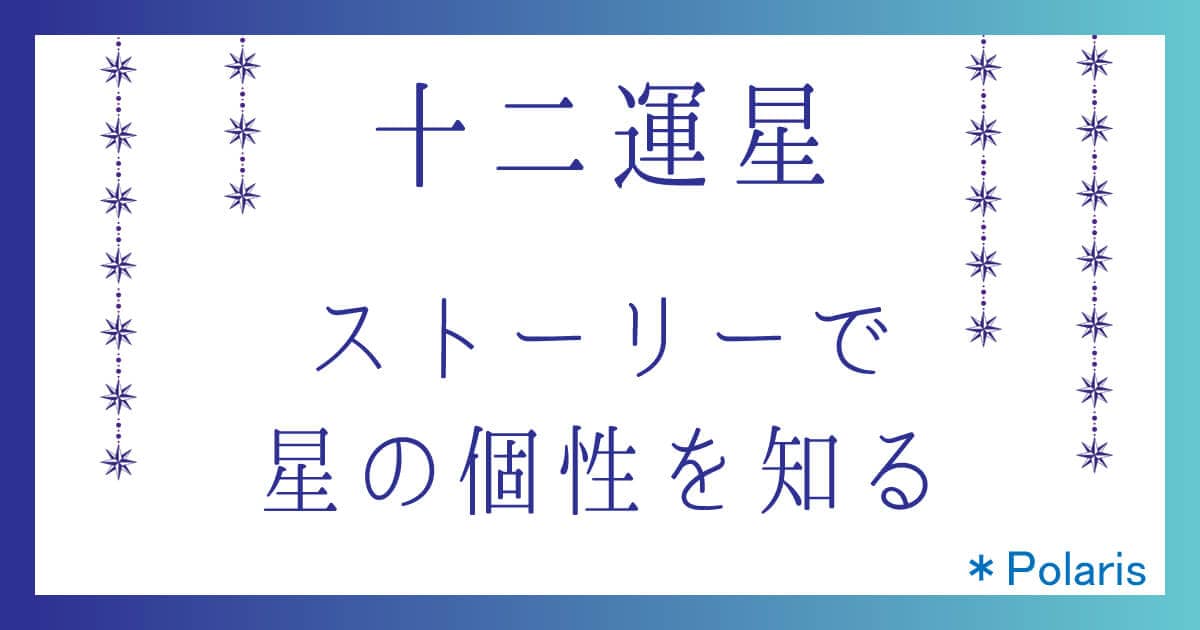

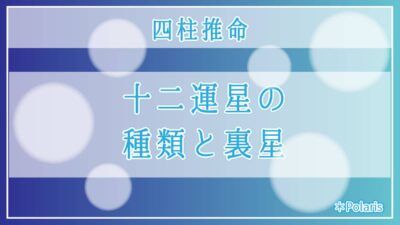

コメント
コメント一覧 (1件)
こんばんは。
新暦より、旧暦の誕生日で命式を出す方が
しっくりきます。
新暦だと日柱は甲寅の比肩建禄。
安定的にコツコツ継続していくがピンと来ず、
旧暦だと日柱は庚午の印綬沐浴。
気になることは1日中、調べたり、
伝統芸能の観劇や海外に一人旅に
行くこともあります。好きな国に想いを馳せるのが
楽しいです。
母の価値観や考えに縛られ、身動きが
取れなくなります。過干渉で口出しをされます。
印綬沐浴の方が私にピッタリなのですが、
皆さん、新暦の誕生日で命式を出されているん
ですよね?家族や知人、有名人を新旧暦の両方で
命式を出して見てみましたが、旧暦の方が
納得できます。